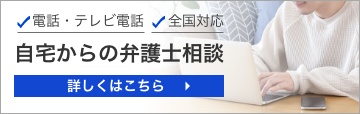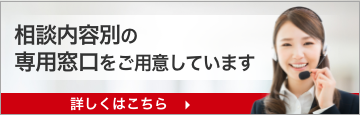損害賠償請求は無視しても大丈夫? その後の展開や対処法を弁護士が解説
- 一般民事
- 損害賠償請求
- 無視

京都地方裁判所事務局の統計資料によると、令和3年に京都地方裁判所および市内簡易裁判所が取り扱った、民事・行政事件の訴訟件数(新受件数)は、9438件でした。この件数のなかで大多数を占めるのが「損害賠償請求」でしょう。
損害賠償請求を受けると、訴訟を経て最終的に、相手に◯◯万円を支払う、という判決が下されます。しかし、裁判所の判決であっても、そのお金を用意できない場合もあります。また、それなりの言い分もあって「支払いたくない」というケースも存在します。
しかし、損害賠償請求を踏み倒すことは可能なのでしょうか? 損害賠償請求を無視していると、どのような事態に発展してしまうのでしょうか?
本コラムでは「損害賠償請求を無視した場合」をテーマに、想定としてその後起こりうるトラブルや対処法を京都オフィスの弁護士が解説します。
1、まず損害賠償請求を受けた理由を考える
損害賠償請求を受けたら、まずどうするべきなのでしょうか。
ここでは損害賠償請求の基本をチェックしながら、損害賠償請求を受ける具体的なケースについて紹介します。
-
(1)損害賠償請求とは?
「損害賠償請求」とは、他人によって発生した損害について、損害を与えてきた相手に対して償いを求めることを指します。
知人の持ち物を借りていたときに不注意などでそれを壊してしまえば、代金分を支払うかまたは代品を購入して返すはずです。
このような損害の償いを知人側から求める法的な行為が「損害賠償請求」と呼ばれます。
損害賠償請求は、典型的には、相手方に「債務不履行」や「不法行為」があった場合にすることができます。「不法行為」について定めた民法第709・710条を見てみましょう。
【民法第709条】(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
【民法第710条】(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
この条文をみると、わざとであろうと不注意の事故であろうと、財産上のものであろうと身体や名誉であろうと、他人による損害に対してある程度広く「不法行為」に基づく損害賠償請求が可能となっています。
また、損害を賠償する方法は、民法722条1項が準用する民法第417条の規定によって「金銭をもってその額を定める」とされています。 -
(2)損害賠償請求を受けうるケース
損害賠償請求を受けうるケースの具体例を挙げてみましょう。
まず考えられるのが「債務不履行があった場合」です。
- 約束の期日までに代金を支払わなかった
- 納品を約束した日に商品を届けなかった
- 引き渡し日までに不動産を引き渡せなかった
- 引っ越し業者がスケジュールのミスで引っ越し作業ができなかった
「不法行為があった場合」も損害賠償請求を受けえます。
- 暴力を加えてケガをさせた
- お金をだまし取った
- 交通事故を起こしてケガをさせ、相手の車を壊した
- インターネット上で他人を誹謗中傷した
- 既婚者と不倫した
- 部下にパワハラをはたらいた
また、債務不履行と不法行為の両方が同時に成立してしまうケースもあります。
- 引っ越し業者が作業中に家具を壊してしまった
- 運行中のタクシーが交通事故を起こして乗客がケガをした
これらのケースでは、いずれも「契約に対する債務不履行」と「過失による不法行為」が同時に成立しており、当然この場合も、損害賠償請求を受ける可能性があります。
2、損害賠償請求を無視したらどうなる?
一部では「損害賠償請求は踏み倒せる」といった情報があるようですが、本当に可能なのでしょうか?
損害賠償請求を無視していたらどうなるのか、一般的な流れや結末をみていきましょう。
-
(1)損害賠償請求の流れ
損害賠償請求は、段階的に請求の方法が変化します。
●債権者・債務者間の請求
債権者(お金を請求する権利がある者)から、電話、メール、手紙などの方法で「賠償してほしい」という請求を債務者(お金を支払う義務を負う者)は受けます。
●内容証明郵便の送付
前述した債権者・債務者間の請求でも賠償がなければ、内容証明郵便が郵送されてきます。
内容証明郵便を送付することで、いつ、どのような請求をしたのかが明確になり、債権者には「請求した」という証拠が残ります。
●裁判所からの通知
裁判所から「損害賠償請求の訴えを受けた」という事実が通知されます。
裁判所から債務者に対して通知されているということで、債権者が裁判所に訴訟を提起したことが分かります。 -
(2)裁判所の呼び出しを無視した場合はどうなる?
裁判所からの通知には「答弁書」が同封されています。
裁判所は「まずはあなたの主張を聞きましょう」という姿勢をとるわけです。
やむを得ない事情があればその旨を、反論があればその内容を整理して答弁書に記載し返送する必要があります。
ところが、これを無視して答弁書を返送せず、さらに指定された期日も無視して裁判所に出頭しなかった場合は、原告(債権者)の請求および主張がすべて認められてしまうおそれがあります。
裁判所の判決を得た債権者は、強制執行の申し立てによって債権の回収を図りえます。
強制執行を受けてしまえば、預貯金などの財産や給与の差し押さえを受けるリスクを背負ってしまいます。
以上のような事情を鑑みれば、損害賠償請求を「無視していれば踏み倒せる」といった対処は間違いということをご理解いただけたのではないでしょうか。
裁判所の通知や呼び出しを無視すると自分自身が不利益を受けてしまうので、早急な対処が必須であると心得ておきましょう。
3、心当たりがないときの対処法
なぜ損害賠償請求を受けたのか、心あたりがまったくない場合はどのように対処するべきなのでしょうか。
-
(1)正当な方法で反論する
心あたりがない請求であっても、そのまま無視してはいけません。
本当の裁判所からの通知であれば、通知を無視して放置すると、不利益を受けるおそれがあります。裁判所の手続きはすぐには進行しませんから、まず落ち着いて、本当に裁判所からの通知であるか確認する必要があります。
正式な通知や訴状が裁判所から送達されたにもかかわらず、これを無視していると最終的には相手の主張が100%認められてしまう可能性が高いため、たとえ架空の事実に基づいた損害賠償請求であっても最終的に支払いの義務が生じかねません。
裁判所からの通知を受けたら、答弁書に「心あたりがない」という趣旨の内容を書いて返送し、反論しましょう。 -
(2)弁護士に相談する
損害賠償請求に心あたりがないときであっても、すぐに弁護士に相談することは有益です。
法律の専門家である弁護士なら、相手の賠償請求が正当なものなのか、どのような内容で答弁書を作成するべきなのかなどのアドバイスが得られます。
また、訴訟対応のすべてを弁護士に任せることも可能です。
こちらにはまったく心あたりがない請求でも、相手にとっては「正当な請求だ」と主張できる材料があるのかもしれません。
証拠の提示や反論の方法によっては、相手の主張が認められてしまい支払いの判決が下されてしまうおそれがあります。
心あたりがまったくないからこそ、毅然(きぜん)とした対応が必要だと心得ておきましょう。
4、心当たりがあるときの対処法
損害賠償請求に心あたりがあっても「仕方がない」とすべて受け入れるのではなく、最善を尽くすことをおすすめします。
-
(1)交渉の余地があるのかを検討
請求に心あたりがある場合でも無視するという行為は避けるべきです。
心あたりがある正当な請求であっても、交渉の余地があれば減額や猶予を求めることで負担が軽減できる可能性があります。
たとえば、交通事故を理由にした損害賠償請求であれば、修理にかかった費用が相場を超えてあまりにも高額である、相手にも過失があったはずといった反論が考えられ、交渉の余地があるかもしれません。
-
(2)頼るべきは弁護士
たとえ心あたりがある請求であっても、相手の請求を鵜呑みにするのは得策ではありません。
とはいえ、減額や猶予を求めても容易に相手が納得するとは考えにくいので、まずは弁護士への法律相談がおすすめです。
弁護士に相談すれば、減額や猶予を求める材料がないか、反論によって支払いの回避が期待できるかといった点についてアドバイスが得られます。
さらに、実際に弁護士と契約し、相手への対応や訴訟の手続きをすべて任せれば、答弁書や準備書面の作成を行ってくれますし、必要な事実を立証し、主張を展開してくれますので、賠償責任の範囲や金額を抑えることが期待できます。
5、まとめ
突然、裁判所から「損害賠償請求訴訟の提起を受けた」という通知がくれば、誰でも驚いてしまうはずです。
なかには「支払えないし無視しよう」「無視を続ければ踏み倒せると聞いたことがある」と通知を無視してしまう方もいますが、相手の請求がほぼすべて認められてしまうため、最終的には自分が不利益を被ってしまいます。
損害賠償請求を受けてしまったら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、請求に心あたりがある場合も、あるいはない場合でも、どのように対処すべきかについて適切なアドバイスが受けられます。
相手への対応や訴訟の手続きを一任すれば、賠償金の減額や支払いの猶予が得られる可能性もあります。
損害賠償請求を受けてしまい対応に困っている方は、ベリーベスト法律事務所・京都オフィスにご相談ください。
数多くの損害賠償請求トラブルを解決してきた実績をもつ弁護士が、請求の正当性や交渉の余地があるのかを判断して、最適な対処法を提案します。
損害賠償請求を受けてしまったら、できるだけ素早い対処が必要です。
ひとりで悩むよりも、まずはベリーベスト法律事務所・京都オフィスまでお気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています