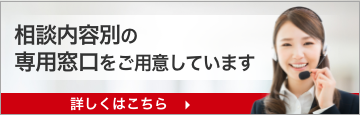業績悪化で契約社員を更新しない。 会社側が気を付けるべき雇止めの注意点を解説
- 一般企業法務
- 契約社員
- 更新しない

令和2年度の1年間に京都府内で倒産した企業は246社となっています。新型コロナウイルス感染拡大による観光需要の低下の影響もあるとみられ、令和元年度を5%上回り3年ぶりに増加しています。
新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少する中、会社が人員整理を行う動きは京都府内だけでなく日本中でみられます。
会社側としては、人員整理により正社員を解雇することは難しいとしても、契約社員・パートタイマー・派遣社員などの非正規職員であれば、容易に雇用関係を終了させられると考えるかもしれません。
しかし、非正規職員であっても労働者の権利は法律上強く守られており、会社側の一方的な都合だけで、退職させることは出来ません。とりわけ、更新が繰り返され正社員に近い地位にある非正規職員の場合、期間途中での解雇はもちろん、次の契約更新を拒絶し雇止めをすることは、法律上の強い制約を受けます。
では、会社側は経営状態がどれだけ悪化したとしても、非正規職員との雇用関係を終了できないのかといえば、そうではありません。
本コラムでは、非正規職員、とりわけ契約期間が予め定められている契約社員について、雇止めのルールや適用の注意点を中心に、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士がご説明します。
1、「雇止め」とは
労働契約にはさまざな形態がありますが、期間に注目した場合、「無期労働契約(期間の定めがない契約)」と「有期労働契約(期間の定めのある契約)」に大別されます。
無期労働契約を締結した労働者は、正社員(フルタイム・無期雇用労働者)である場合が多く、一方、有期労働契約を締結した労働者は、契約社員などと呼ばれ、契約期間ごとに同じ内容で更新されるというケースが多いでしょう。
そして「雇止め」とは、契約社員等、有期雇用労働者について、契約期間満了後に次の更新をせず、そのまま雇用関係を終了させることをいいます。
以下では正社員と契約社員それぞれについて、解雇や雇止めに関する違いを説明します。
-
(1)正社員の解雇
会社には、労働者を解雇できる「解雇権」が認められています。解雇には大きく「普通解雇」と「懲戒解雇」に大別されます。普通解雇の代表的なものとしては、労働者の能力不足や適格性の欠如、会社の業績悪化による整理解雇、等があります。
もっとも、いくら解雇権があったとしても、解雇について、法律上以下のような厳しい規定が設けられ、簡単に解雇することは出来ません。- 解雇に、客観的合理性があり、社会通念上相当であること(労働契約法第16条)
- 労働者に対して30日前に解雇を予告するか、30日分以上の解雇予告手当てを支払うこと(労働基準法20条)
- 解雇制限期間(業務上の負傷・疾病により休業中、産前産後の休業中)ではないこと(労働基準法19条)
- 懲戒解雇の場合は、解雇事由が、あらかじめ就業規則等に定められていること(労働契約法15条)
これらの規定に反する解雇は無効となります。
-
(2)契約社員の解雇
契約社員の場合は、期間を定めて契約した以上はその期間を全うすることが原則であるため、契約期間の途中で解雇する場合には、正社員の解雇よりも、より強い理由が必要です。期間満了を待っていられないほどの、強度のやむを得ない事由が要求されます。
-
(3)契約社員の無期雇用契約への転換
雇止めについて詳しくお話する前に、まずは、前提として押さえるべき法律上の規定として、有期雇用契約の無期雇用契約への転換について、ご説明します。
平成20年台半ば、急速な少子高齢化の進展による労働力不足、非正規労働者の増大という社会問題が顕在化し、非正規労働者を保護する動きが高まりました。そして次々と非正規労働者の保護を目的とした法律が新しく制定改訂されるようになります。
そのうちの一つとして、平成24年に労働契約法の一部が改正され、次の条件を満たした場合には、無期雇用契約へと転換できることになりました(労働契約法18条)。- これまでの有期労働契約の通算期間が、5年を超えていること
- これまで労働契約を更新した回数が、1回以上であること
- 有期雇用契約の期間満了前に、転換の申し入れがあったこと
この制度により、人材不足に悩む業界では有期雇用労働者を無期雇用労働者へと転換させる動きが起きました。
その一方で、転換を制限したい会社では、契約期間が通算5年になる前に、次の更新をせず雇止めをする動きが相次ぎ、問題視されました。
本来、有期雇用労働者との労働契約は、契約日の満期が来ることで自動的に終了となります。(なお、契約を3回以上更新している場合、または、雇い入れから1年を超える場合については、労働契約終了の30日前までに更新しない旨の予告が必要です。)
そして、会社側には、契約を更新しなければならないという義務はありません。ですので、一見すると雇止めには問題がないように思えます。
しかし、契約更新を繰り返し、仕事内容や責任も正社員に近いものであった労働者の場合は、雇止めを受ければ、事実上、正社員の解雇と同様のダメージを受けます。ですので、通常の契約社員よりも、より強い法律上の保護を受けることになるのです。では、どのような場合に雇止めが無効、または有効となるなのか、詳しくみてみましょう。
2、「雇止めの法理」の法定化と対象となる労働者
-
(1)「雇止めの法理」の法定化
かつては、有期雇用労働者の雇止めについて明確な規定が存在せず、判例を蓄積して形成された「雇止めの法理」という考え方を用いて、不合理な雇止めを制限し、有期雇用労働者を保護していました。
しかし、非正規労働者の要保護性の高まりを受け、平成24年8月には、「雇止め法理」が、労働契約法第19条として法定化されたのです。その内容は、契約社員などの有期雇用労働者のうち、契約更新が反復され無期雇用労働者の解雇と同視できる場合、かつ、有期雇用労働者が更新を期待することが合理的である場合には、雇止めについて、より強い制約を設ける、というものです。 -
(2)対象となる労働者
具体的には、次のような有期雇用労働者が当てはまります。
- 通算契約期間が長い
- 更新回数が多い
- 契約書が存在しない、契約書がある場合でも2回目以降の契約書は作成されず自動更新となっている
- 会社が「有期雇用だがよほどのことがない限り契約は更新される」、と説明したり、「定年まで頑張って下さい」、などの声掛けをしていた
これとは逆に次のような場合であれば、雇止めの制限が緩やかになる可能性があります。
- 業務内容や責任が正社員よりも軽い、または、臨時的な特定の業務に従事している
- 採用条件が緩やか
- 採用時に契約や更新について明確な説明があった
- 更新ごとに契約書が新たに作成されている、更新回数に上限がある
- 正社員登用制度を受けたが登用されなかった
3、雇止めで気を付けるポイント
-
(1)雇止めが出来る場合もある
前述したように、更新が繰り返され無期雇用労働者と同視できる有期雇用労働者は、なかなか雇止めをすることは出来ません。とはいえ、雇止めが可能な場合もあります。それは、労働契約法19条に明文化されているとおり、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当な理由」があるといえる場合です。
では、どのような場合であれば、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当な理由」ある、つまり雇止めが可能となるのでしょうか。 -
(2)判断基準
これは、正社員を解雇する際に必要な事由と概ね同じように考えられています。そして、客観的合理性や社会通念上の相当性は、以下のような観点で判断されます。
- 当該有期雇用労働者の労働契約を継続することで、会社の業務や社会に与える影響の度合い
- 会社の業況悪化、あるいは事業構造改革のために、どうしても雇止めが避けられないこと(整理解雇の場合には、正社員を解雇するより先にまず契約社員を雇止めすることは、合理性があると考えられます。)
- これまでの当該雇用労働者の会社への貢献度合い
- 有期雇用労働者の雇用を継続するために、会社が講じた措置の有無およびその内容
- 問題行動を理由に雇止めする場合には、反省の有無や過去の処分歴、および当該問題行動が会社に与えた影響
- 就業規則や労働契約に雇止めとなる事由が明記されているかどうか、当該労働者がそれに該当するかどうか(就業規則は、書面を交付する、書面を交付しない場合は職場の分かりやすい場所に掲示したり、手に取りやすい場所に保管されていたりなど、労働者に周知されていることが必要です。)
-
(3)雇止めに関する会社のリスク
このように、有期雇用契約であっても、簡単に解雇や雇止めすることは出来ません。それどころか、無期転換ルールに該当する労働者が無期雇用契約を申し入れた場合には、会社はそれを拒むことは出来ません。これは、人件費の抑制目的や人材の流動化目的で有期雇用契約を結んだ会社にとっては、頭の痛い問題かもしれません。
しかし、強引に雇用関係を終了させようとすると、雇止めや無期転換ルールなどの適用をめぐりトラブルが生じかねません。その場合、会社はその対応に相応のコストを割かなくてはならず、話し合いで解決できず裁判までに発展し雇止めが無効とされた場合には、当該労働者が休職中であった期間の給与や、損害賠償金を支払わなければならない可能性があります。また、コスト面だけでなく、会社の社会的信用や評価に悪影響をおよぼすリスクもあります。
このように、非正規社員との労働契約に関する問題についても、正社員と同じように気を配る必要があります。そして、生じる可能性のあるトラブルについては、事前に十分な対策をして準備しておくことが重要です。
4、まとめ
労働関連の法令や制度は頻繁に改正が行われており、さらに年々複雑化しています。そのトレンドは、会社と比べて弱い立場にある労働者の保護を図ることで一貫しています。それに比例して、会社側が対応しなくてはならないことも増えています。
日々の業務に忙しい経営者や人事労務の実務に携わる方にとって、法律の改正や新しい制度をタイムリーにキャッチアップし、それに対応することは、決して容易ではありません。そのようなお悩みをお持ちの方々にとって、弁護士は会社の心強いパートナーになります。
ベリーベスト法律事務所では、会社が抱えているさまざまな問題にワンストップで対応することができる顧問弁護士サービスを提供しています。もちろん、労働問題にかぎらず、幅広い範囲でご対応させていただくことが可能です。
労働関連のご相談は、ぜひベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでお気軽にご依頼ください。貴社のために、ベストを尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています