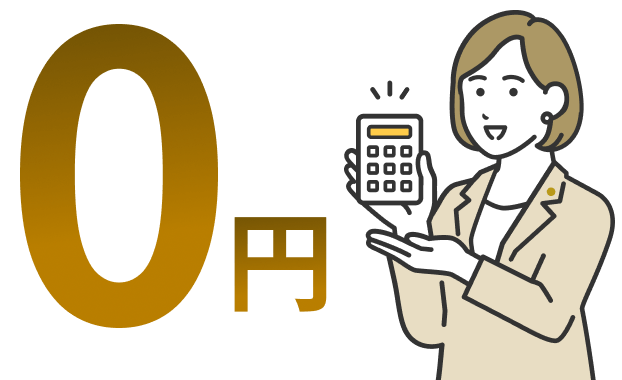相続の廃除とは? 認められた場合の相続について、京都オフィスの弁護士が解説
- 遺産を残す方
- 相続
- 廃除

有名な企業や大きな会社の経営者一族であっても、相続、遺言で揉めることが少なくありません。平成18年、京都の老舗カバンメーカーの相続トラブルが注目を集めました。
一般家庭における相続トラブルもけっして珍しいことではありません。財産を分割する割合だけでなく、そもそも「相続させるかどうか」自体が問題になることもあります。
本記事では、特定の人物に遺産を与えない「相続廃除」の手続きについて京都オフィスの弁護士が解説します。
1、相続廃除の手続きとは? 概要と要件を解説
まずは相続廃除が何のために存在しているのか、手続がどのように進められるかを把握した上で、その後の対応を検討していきましょう。
-
(1)相続廃除の手続きの概要
財産の多寡に関わらず、人が死亡すると相続の手続きを行うことになります。
財産を誰に相続させるかは、遺言によって亡くなった本人が自由に決めることができますが、配偶者、子、直系尊属については、「遺留分権」という遺産の一定割合を確保する地位が認められています。その「遺留分権」すらも奪うための手続きが「相続廃除」と呼ばれるものです。
●相続廃除の効果
相続排除について、たとえば「父親が死亡した場合」で考えてみましょう。
父親が死亡して、母親と子ども2人(長男、次男)がいた場合、計3人が相続人となります。
父親が、「次男には相続させたくない」と考えた場合に、まず検討するのが遺言になります。
たとえば、遺言書に「妻に2分の1、長男に2分の1を相続させる」と記載されていた場合、その遺言書は有効です。次男がその内容に納得すれば、父親の意思どおりの相続が行われます。しかし、次男が相続人の最低限の取り分「遺留分」を請求した場合、遺留分侵害額につき、請求が認められることになります。
この場合、相続廃除が認められれば、次男は遺留分権が剥奪されるため、次男に遺産が行きわたることはなくなります。
●相続廃除の方法
相続廃除をするためには、「被相続人」が以下のいずれかの手続きを行う必要があります。
・被相続人が家庭裁判所に申し立てをする
家庭裁判所での手続きは「審判」という形式で行われます。
相続の廃除を認める審判がなされた場合、申し立てを行った被相続人は、家庭裁判所が作成した書類を役所に提出しなければなりません(戸籍法第97条、第63条1項)。届出がなされることで、当該相続人が相続人から廃除されます。
・被相続人が遺言書に廃除する旨を記載する
被相続人が遺言書に当該相続人の廃除の旨を記載した場合は、遺言執行人が家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行うことになります。
なお、被相続人は遺言書で相続廃除を実行する場合は、あらかじめ遺言執行者を選任しておく必要があります。遺言執行者がない場合は、相続人などの利害関係人が、遺言執行者の選任を求めることになります(民法第1010条)。 -
(2)相続廃除が認められる要件
相続廃除の対象者は、遺留分権を有する相続人です(民法第892条)。亡くなった被相続人のきょうだい(兄弟姉妹)は、そもそも遺留分権はありませんので、対象ではありません。きょうだいに遺産を分け与えたくない場合は、きょうだいに分け与えることのないような遺言を作成すれば良いのです。
被相続人の意思が全て反映されて、相続廃除が常に認められるわけではありません。以下の要件を満たしている場合に、家庭裁判所から相続廃除が認められます。
●被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合
被相続人への虐待とは、暴力や耐え難い精神的苦痛を与えることです。
重大な侮辱とは、被相続人に対する名誉の毀損や感情を大きく害する行動を指すものです。
具体的には、「親に多額の借金を肩代わりさせた」、「親に対して暴言をはいた」、などの場合に、虐待や重大な侮辱とみなされる可能性があります。
●相続人にその他著しい非行があった場合
「相続人の著しい非行」とは、犯罪行為、相続人による被相続人の遺棄、財産の浪費、不貞行為、長期の音信不通といった行為です。
犯罪行為に関して、親でなく他者への犯罪行為は、重大な非行に当たらない可能性もあります。
2、相続廃除と相続欠格の違い
相続廃除と似た用語に「相続欠格」というものがあります。
「相続欠格」とは、相続人に、重大な犯罪行為や相続に関して悪質な行為があった場合に、相続秩序を乱したものとして、相続する権利を法律上当然にはく奪する民事上の制裁を指します。
相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に申し立てたり、遺言書に記載したりすることで特定の相続人の遺留分権を奪うものです。一方で相続欠格は、「被相続人による手続きがなくても」相続人としての権利を当然に失うことになります。
民法では相続欠格となる場合を以下のとおり規定しています。
- 被相続人や、同順位以上の相続人を殺そうとした(未遂)、殺した
- 被相続人が殺人の被害に遭っていたことを知りながら、告発しなかった
- 詐欺や脅迫により、被相続人の遺言を取り消し、変更、妨害した
- 詐欺や脅迫により、被相続人の遺言の取り消し、変更を邪魔した
- 遺言書を偽造したり、書き換えたり、隠したり、廃棄したりした
これらのケースに該当する場合は、被相続人による手続きがなされなくても、相続人の権利を失います。
3、一度認められた廃除を取り消す方法は?
家庭裁判所で廃除が認められた場合でも、「被相続人の意思が変われば」、以下の方法で相続の廃除を取り消すことができます。
- 被相続人が家庭裁判所に相続廃除の取消を申し立てる
- 被相続人が遺言書に相続廃除を取り消す旨を記載する
いずれの場合も、「被相続人が相続廃除を取り消す意思を表示」しなければなりません。
相続人自身が廃除を取り消してほしいと思った場合に、廃除を取り消すために直接行える手続きはありません。廃除された相続人が、被相続人に対して廃除を取り消すようにと交渉することになります。
4、廃除されても遺産を受け取れるケースは?
相続人がもし廃除を受けた場合、その廃除が取り消されなくても遺産を受け取れる方法はあります。
-
(1)遺贈は受け取ることができる
相続廃除の対象者となった場合でも、遺言書に遺贈する旨が記載されていれば、財産を受け取ることができます。
家庭裁判所への廃除の取り消しの申し立てが間に合わない場合でも、被相続人にあなたに遺贈する旨の遺言書を記載してもらえれば、財産を受けとることが可能になります。 -
(2)自分に子どもがいれば代襲相続される
相続廃除とされた場合でも、子どもがいれば、「代襲相続」によって財産を受け取ることができます。
代襲相続とは、相続人が相続廃除された場合や、死亡した場合にその子どもが代わりに相続することをいいます。
5、相続廃除をされた、されそうで困っている方は弁護士に相談を
自分の父親や母親、配偶者などに相続廃除の手続きをなされた場合、または相続廃除される可能性がある方は、弁護士への相談をおすすめします。
相続廃除を検討している被相続人との関係は、複雑にこじれている可能性が高く、当事者同士では難しい交渉でも、弁護士を介することでスムーズに進む可能性があります。
-
(1)相続廃除の手続き前であれば、被相続人との交渉が可能
被相続人が相続廃除の手続きを申し立てる前であれば、弁護士は相続廃除が不適当である旨を被相続人側と交渉することができます。
相続廃除が認められる要件は、一概に決められるものでありません。一度の暴言や被相続人の名誉を害する発言だけでは、相続廃除の要件を満たしているとはいえません。
相続廃除が適当ではない場合には、弁護士を介した交渉で相続廃除の手続きを阻止できる可能性があります。 -
(2)相続廃除の審判を申し立てた場合は、弁護士が証拠を用意して対抗できる
すでに、被相続人が相続廃除の審判を申し立てている場合は、弁護士が相続廃除の要件を満たしていないことを主張することで、申し立てが却下される可能性があります。
相続排除の審判は、被相続人(申立人)が廃除事由を具体的に記載した申立書とこれを裏付ける証拠資料を提出して、申し立てがなされます。これに対して、廃除されようとしている相続人は、反論書面とこれを裏付ける証拠資料を提出することになります。こうした書面のやり取りと実際の裁判官からの聴き取り(審問)が行われて、最終的に、廃除が認められるかどうか判断がなされます。
上に述べたような主張のやり取りについて、法的な書面を作成したり、証拠を収集したりというのは、本当に大変です。書面の作成や証拠の収集について、弁護士の力を借りることで、裁判官に分かりやすく主張を伝えることができますし、必要な証拠を的確に集められる可能性が高まります。 -
(3)相続廃除が認められた後の交渉
相続廃除が認められている場合でも、弁護士によって、相続廃除の取り消しや遺言書に遺贈する旨を記載してもらう交渉を進めることができるかもしれません。間に弁護士が入ることによって、当事者が話すよりも感情の対立が和らぐ場合もあるかもしれません。
6、まとめ
相続廃除となると、廃除された相続人は遺留分の請求ができなくなります。
また、相続廃除の審判がなされた場合、廃除された相続人本人が廃除の取り消しを求めることはできません。
しかし、被相続人に対して、廃除の取り消しを交渉し、遺言書に遺贈する旨を記載してもらえれば財産を受け取ることは可能です。
いずれの場合も、被相続人との粘り強い交渉を避けることはできませんので、相続トラブルの経験が豊富な弁護士への相談が、解決への有効な手段のひとつとなります。
ベリーベスト法律事務所 京都オフィスでは相続の廃除に関するご依頼も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています