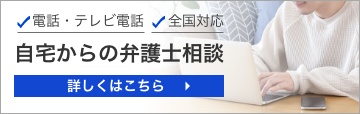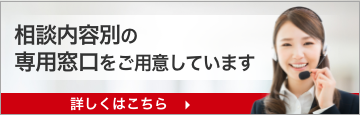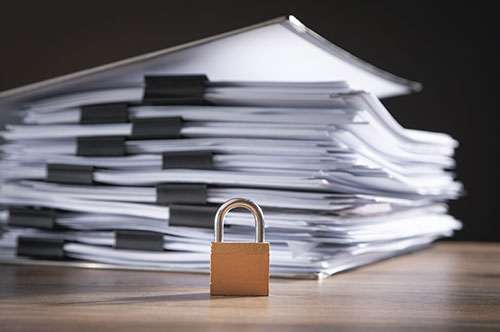取締役(会社役員)を辞任する方法・注意点について弁護士が解説
- その他
- 役員
- 辞任

京都府統計書によると、平成28年6月1日時点における京都府内の事業所数は11万3774件で、4年前の平成24年2月1日時点の11万7884件に比べて若干減少しています。
その一方で、国の試算した売り上げ(収入)金額では、平成24年2月1日時点の21兆7818億4400万円に対して、平成28年6月1日時点では25兆4033億6000万円と、増加に転じているのが特徴です。
健康上の理由などにより、任期の途中で取締役(会社役員)を辞任したい場合には、タイミングと手続きについて留意すべき点があります。
この記事では、取締役(会社役員)を辞任する方法や注意点について、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「市区町村別、産業大分類別事業所数と従業者数(全事業所)」(京都府オープンデータポータルサイト))
1、取締役の任期が満了すれば自動的に退任する
取締役を退任する方法には、自ら辞任する場合のほかに、任期満了により退任する場合があります。
任期満了による退任は、辞任とは法律上の位置づけが異なりますので、両者の基本的な違いを理解しておきましょう。
-
(1)取締役の任期は何年?
会社法上、取締役の任期は原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」とされています(会社法第332条第1項本文)。
どの時期に取締役に就任したかにもよりますが、おおむね2年前後と理解しておけば良いでしょう(委員会設置会社の場合は、例外的に「1年」となります(同条第3項、第6項))。
ただし、定款または株主総会の決議によって、この任期を短縮することが認められています(同条第1項但し書き)。
また、非公開会社については、定款によって任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができます(同条第2項)。
具体的な任期については、自社の定款や過去の株主総会決議の内容を確認しましょう。 -
(2)任期満了の場合は辞任の手続きは不要
取締役の任期が満了した場合、再任されない限りは、特段の手続きを要することなく自動的に退任します。
そのため、任期満了で退任する際には、特に辞任したい旨の意思表示をする必要はありません。
2、任期満了前に取締役を辞任する方法は?
取締役の任期が満了する前に、さまざまな理由から取締役を辞任したいと考える場合もあるかもしれません。
たとえば、
- 健康の悪化により、取締役としての業務を満足に遂行できない
- 会社の経営方針と自分の考え方の間に相違がある
- 別の会社からヘッドハンティングの誘いを受けている
などの理由が考えられます。
このように、任期満了を待たずして取締役を辞任する場合、どのような方法を採るべきかについて解説します。
-
(1)取締役はいつでも辞任できる
株式会社の取締役は、いつでも自分の判断で辞任することが可能です。
取締役と会社の間には、民法上の「委任」関係が存在すると解されています(民法第643条)。委任契約に関する解除ルールを定める民法第651条第1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」と規定しています。
受任者である取締役側からの解除については、会社法上、上記の規定を修正する条文は存在しません。そのため、民法・会社法の規定に照らすと、取締役はいつでも自分の裁量によって、委任契約を解除して辞任できるということになります。
なお、委任契約の中で、取締役側からの一方的な辞任を制限する条項が設けられることがあります。
しかし、大阪地裁昭和63年11月30日判決(判例時報1316号139頁)では、取締役の辞任の自由を制約する特約は無効であるという判断が示されています。 -
(2)代表取締役に対して辞任の意思表示をする
代表取締役以外の取締役が任期途中で辞任する場合、代表取締役に対する辞任の意思表示が必要です(東京高裁昭和59年11月13日判決判例時報1138号147頁)。
意思表示の形式は法律上決まっておらず、口頭の意思表示でも有効ですが、確実に辞任の旨を伝えるためには、辞任届を書面で作成して提出するのが良いでしょう。 -
(3)代表取締役自身が辞任する場合の手続きは?
これに対して、代表取締役自身が任期途中で辞任する場合は、意思表示の相手方に関するルールが異なります。
まず、他に代表取締役がいる場合には、その代表取締役に対して辞任の意思表示をすれば足ります。この場合は、通常の取締役が辞任する場合と同様に、辞任届を書面で作成して提出すればOKです。
しかし、多くの会社では代表取締役は1人なので、その場合は取締役会設置会社においては取締役会を招集して、その場で辞任の意思表示をする必要があります(東京高裁昭和59年11月13日判決判例時報1138号147頁)。他の方法で自身以外の取締役全員に辞任の意思が了知された場合も辞任の効果が認められることがあります(岡山地裁昭和45年2月27日判決金融法務事情579号36頁)。
取締役会において辞任の意思表示をした場合には、議事録にその旨を記載しておきましょう。
3、取締役を辞任する場合の注意点
前述のとおり、取締役はいつでも自分の判断で辞任できますが、その際は、辞任に関する法律上のルールにも気を配ることが大切です。
取締役の辞任に関する、民法・会社法上の注意点を見てみましょう。
-
(1)辞任のタイミングによっては損害賠償責任を負う可能性がある
取締役が独断で辞任したことにより、会社の業務に穴が開いて損害が発生する場合もあります。
民法第651条第2項第1号本文によると、取締役が会社にとって不利な時期に委任を解除した場合には、取締役が会社に生じた損害を賠償しなければなりません。
たとえば、取締役が会社から重要なプロジェクトを任されていたのに、進捗(しんちょく)半ばで突然辞任したという場合が典型例でしょう。
ただし、委任の解除(辞任)についてやむを得ない事由があったときは、取締役は会社に対する損害賠償責任を負わないとされています(同項但し書き)。
特に、健康の悪化を理由とする辞任の場合は、病状の程度にもよりますが、やむを得ない事由があると認められる可能性が高いでしょう。 -
(2)取締役に欠員が出る場合は、後任が就任するまで職務を行う
会社の定款においては、取締役の最低人数が定められています。
取締役の辞任によって欠員が生じてしまう場合には、辞任する取締役は、後任の取締役が就任するまでの間、引き続き役員としての権利義務を有します(会社法第346条第1項)。
この場合、辞任の意思表示にかかわらず、後任の就任までは、会社の経営に対して責任を負わなければならないので注意が必要です。 -
(3)辞任の事実は登記がなければ第三者に対抗できない
取締役の氏名は、株式会社の登記事項とされています(会社法第911条第3項第13号)。
そのため、取締役の辞任は、その旨を登記した後でなければ、善意の第三者に対抗することができません(同法第908条第1項)。
たとえば、辞任の事実を知らない第三者から取締役としての責任を追及された場合に(会社法第429条第1項)、退任登記が行われていなければ、「もはや取締役ではないから」という理由で責任を免れることはできないのです。
よって、辞任の意思表示を行った後は、法務局に対して変更登記申請書を速やかに提出するよう、会社に対して要請しましょう。
もし会社が協力してくれない場合には、訴訟によって会社に登記手続きを行うことを命じる方法も考えられるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
4、穏便に辞任できそうにない場合には弁護士に相談を
法的には、辞任は取締役自身の判断によって自由に決められるとはいえ、円満退任でないという場合もよくあります。
たとえば、
- 辞任に関して会社から損害賠償を請求されそう
- 会社が後任の取締役を選任しようとしない
- 会社が辞任の登記に協力してくれない
など、会社との間で想定されるトラブルには、さまざまなパターンが考えられます。
辞任に関して会社との間でトラブルになると、会社からの損害賠償請求に加えて、第三者との関係で思わぬ責任を負うリスクを抱えることにもなりかねません。
取締役の辞任に関して、もし会社ともめ事に発展しそうな場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士は、会社との間でトラブルは生じている原因を分析したうえで、会社との交渉や法的措置を通じて、依頼者を法的なリスクから解放するよう進めることが可能です。
5、まとめ
株式会社の取締役は、所定の方法により会社に対する意思表示をすることで、いつでも辞任することが可能です。
しかし、辞任のタイミングによっては会社から損害賠償請求を受けてしまうほか、後任就任のタイミングや登記手続きとの関係で法的な問題点が残ります。
そのため、辞任に関して会社とのトラブルに発展した場合には、できる限り円満・穏便な形で解決を図ることが大切です。
ベリーベスト法律事務所では、企業法務を専門的に取り扱うチームが、会社法に関連する法務全般を担当しています。
会社からのご依頼だけでなく、取締役(役員)個人の方からのご依頼も歓迎しており、依頼者のお悩みを真摯(しんし)に解決へと導いて参ります。
取締役の辞任に関して会社とトラブルになりそうな方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 京都オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています