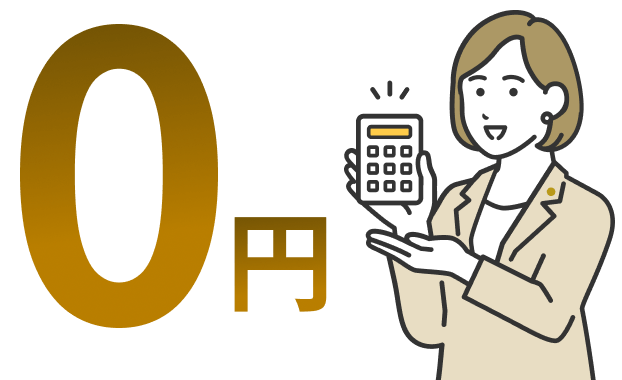山林の相続における法律・相続税に関する注意点を解説
- 遺産を受け取る方
- 山林
- 相続

人口動態総覧のデータによると、2019年中の京都府内の死亡者数は2万7025名で、前年比371名の増加となりました。
山林は、地方在住の方が相続問題を処理するにあたり、農地と並んで取り扱いに注意しなければならない「財産」といえます。
相続財産に山林が含まれている場合、通常の財産を相続するケースに追加した手続きが必要となります。
また、相続税の計算方法なども通常の財産とは異なる点もあるので、法律・税務の観点から正しい処理方法を押さえておきましょう。
本コラムでは、山林の相続における法律・相続税の各観点の注意事項について、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「令和元年京都府人口動態統計(概数)の概要」(京都府))


1、山林を相続する際の手続き
相続財産に山林が含まれている場合、問題を複雑化させないように、遺産分割協議において適切に処理の方針を定めておく必要があります。
まずは、山林を相続する際に必要となる法律上の手続きについて見ていきます。
-
(1)遺産分割協議で誰が山林を相続するかを決定する
相続発生後には、遺産分割協議を実施して、誰が山林を相続するかを決めなければなりません。
山林経営を行う意思がある相続人がいれば、その人が相続すれば良いでしょう。
しかし、誰も山林を相続したくない場合には、第三者に対して売却したうえで、代金を分けるという方法も考えられます。
なお、山林の相続について遺言が存在する場合には、遺産分割協議を行わなくとも、遺言のとおりに山林が相続されます。 -
(2)市区町村への届け出を行う
山林の所有者が変更となった場合には、新たな所有者が市区町村に対してその旨を届け出る必要があります(森林法第10条の7の2第1項)。
相続によって山林の所有者が変更される場合、遺産分割協議がいつ終わるかによって、必要となる届け出の回数が変わります。
①遺産分割協議が被相続人の死亡日から90日以内に整わない場合
相続が発生すると、相続財産は相続人全員の共有物となります(民法第898条第1項)。
遺産分割協議が被相続人の死亡日から90日以内に整わない場合には、いったん山林が相続人の共有となった旨を、市区町村に届け出なければなりません。
そして、遺産分割協議によって山林を誰が相続するかが決まったら、遺産分割協議の終了日から90日以内に、改めて市区町村に対する所有者変更の届け出をする必要があります。
②遺産分割協議が被相続人の死亡日から90日以内に整った場合
これに対して、遺産分割協議が被相続人の死亡日から90日以内に整った場合には、被相続人の共有になった旨の届け出を省略して、遺産分割協議で新たに山林の所有者となった人が市区町村に対する届け出を1回行えば足ります。 -
(3)法務局で所有権移転登記を行う
山林は不動産ですので、第三者対抗要件を備えるためには所有権登記が必要です。
そのため、遺産分割協議で山林を相続する人が決まったら、遅滞なく法務局で所有権移転登記手続きを行いましょう。
2、山林を相続したくない場合|相続放棄・限定承認のやり方
相続財産の大部分を山林が占めており、利用する予定もないので相続を回避したい場合や、相続財産中に資産を上回る負債があることが懸念される場合などには、相続放棄または限定承認をすることも選択肢に入ってきます。
相続放棄とは、相続財産である資産・負債を一切相続しないという意思表示をいいます(民法第939条)。
一方、限定承認とは、相続財産中の資産の限度で負債を相続するという意思表示をいい、相続した財産がマイナスになってしまうことを防ぐ方法です(民法第922条)。
相続放棄・限定承認のそれぞれの手続きについて解説します。
-
(1)原則として相続開始を知った時から3か月以内の手続きを
相続放棄・限定承認のいずれも、原則として相続が開始したことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法第915条第1項本文)。
期限を過ぎても相続放棄・限定承認が認められる場合もありますが(同但し書き)、家庭裁判所に対して遅れた事情を詳細に説明する必要があるなど、手続きがやや面倒になり、確実に認められるわけでもありません。
そのため、できる限り期限に間に合うように、相続放棄・限定承認をするかどうかの方針を固めておきましょう。 -
(2)相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人の最後の住所地である家庭裁判所において、相続放棄の意思を申述します。
必要書類などは、以下の裁判所ホームページをご参照ください。
(参考:「相続放棄の申述」(裁判所))
なお、相続放棄はそれぞれの相続人の判断で行うことができるので、一部の相続人のみが相続放棄するということも可能です。
相続放棄をしていない相続人がいる場合には、残りの相続人の間で遺産分割協議を行います。
一方、全相続人が相続放棄を行い、さらに誰も相続する人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します(民法第959条)。 -
(3)限定承認の手続き
限定承認も、相続放棄と同様に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対してその意思の申述を行います。
ただし、限定承認は相続放棄とは異なり、相続人全員で行うことが必須です(民法第923条)。
限定承認の必要書類など、手続きの詳細については以下の裁判所ホームページをご参照ください。
(参考:「相続の限定承認の申述」(裁判所))
お問い合わせください。
3、山林の相続税の計算方法
山林が相続の対象となる場合、相続税の金額を計算するに当たっては、山林の相続税評価額を求める必要があります。
山林の相続税評価額は、所在地ごとに「倍率方式」または「宅地標準方式」のいずれかによって求められます。
どちらの方式を用いるべきかについては、以下のサイトから確認することが可能です。
(「純○」「中○」(「○」は数字)と記載されていれば倍率方式、「比準」「市比準」「周比準」と記載されていれば宅地比準方式です。)
(参考:「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」(国税庁))
倍率方式・宅地標準方式における、山林の相続税評価額の具体的な評価方法を見てみましょう。
-
(1)倍率方式の場合
倍率方式の場合、山林の相続税評価額は以下の算式により計算されます。
相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
評価倍率としては、前掲サイトにおいて「純○」「中○」と記載されている部分の、「○」に当たる数字を用います。
-
(2)宅地標準方式の場合
一方、宅地標準方式の場合、山林の相続税評価額は以下の算式により計算されます。
相続税評価額=(その山林を宅地とみなした場合の1㎡あたりの評価額-1㎡あたりの宅地造成費用)×地積
4、山林の相続処理をせずに放置した場合に起こり得る問題とは
遺産分割協議では、山林を含めた全相続財産の配分を決めておく必要があります。
山林の相続に関する話し合いがまとまらないからと、そのまま放置しておくと、以下のような問題が発生するおそれもあるので十分な注意が必要です。
-
(1)相続人が増えて遺産分割協議が複雑になる
山林に関する相続処理が終わらないままに、相続人である人が死亡してしまうと、2段階の相続が発生することになります(数次相続)。
この場合、権利関係が複雑になるうえに、相続人の数も大幅に増えてしまうので、さらに遺産分割協議をまとめることが困難になります。
問題を複雑化させないためにも、遺産分割協議におけるもめ事を棚上げ・先延ばしにすることはやめましょう。 -
(2)管理不行き届きで近隣住民とのトラブルの種になる
遺産分割協議で山林を相続する人を決めないと、誰も山林を「自分の物」として認識しないという状態が続き、山林の管理がおろそかになるケースが多々あります。
そのような状態になった場合、土砂崩れなどによって近隣に被害を及ぼす可能性があります。
遺産分割が完了していない状態では、山林は全相続人の共有ですので、周辺住民とのトラブルについては、全相続人が共同で責任を負わなければなりません。
この場合、トラブルに巻き込まれること自体が煩雑であるのに加えて、どのように対処するか、どのように責任を分担するかなどを巡って、相続人間の紛争が再燃するおそれもあります。 -
(3)山林が活用されないままになってしまう
山林も不動産である以上、一定の利用価値が認められますので、誰も利用しない状態で放置しておくことは望ましくありません。
山林を有効活用するためにも、早めに遺産分割協議を完了して、山林を活用する人を決める必要があります。
山林を自分で経営する気がなくても、第三者に対する譲渡や賃貸など、活用の方策はさまざまです。法律上考え得る不動産の活用方法については、弁護士への相談をおすすめします。
5、まとめ
山林は、市街地の土地や建物などと比べると使い勝手が悪いため、相続の際に押し付け合いになりがちです。
山林の相続を巡っては複雑な法律上の問題が存在するため、不安がある方は弁護士へご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、相続専門のチームにより、複雑な法律問題が絡む相続についても適切に対応いたします。
また、グループ内に税理士も所属しているため、相続税に関するご相談も併せてお受けすることが可能です。
相続に関してお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています