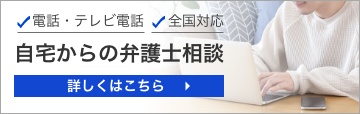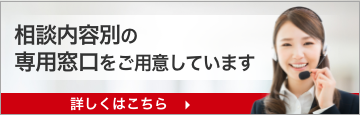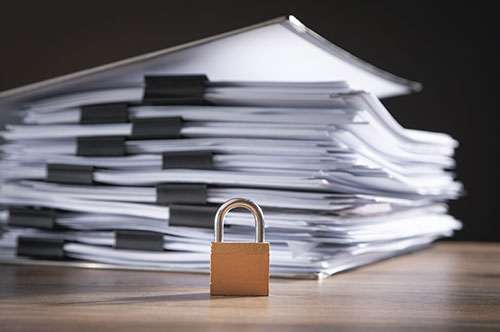債権回収代行とは? 依頼先の業者や弁護士による債権回収の流れを解説
- その他
- 債権回収代行

東京商工リサーチの調査によると、2020年中の京都府内における企業倒産(負債総額1000万円以上)の件数は253件でした。
貸付金や売掛金の回収が滞った場合、自力で債権回収を行うのはかなりの手間がかかりますので、専門の業者に債権回収代行を依頼することをおすすめいたします。
債権回収代行をしている業者には、弁護士をはじめとしていくつかの種類があります。
それぞれの業者には異なる特徴があるので、ご自身に合った業者を選択して依頼しましょう。
この記事では、債権回収代行の概要・依頼先・弁護士による債権回収の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。
(出典:「全国企業倒産状況」(株式会社東京商工リサーチ))
1、債権回収代行とは?
債権回収代行とは、債権が回収できずに困っている債権者のために、専門の業者が債権回収を代わりに行うことをいいます。
債権回収では、債務者の交渉を行うだけでなく、最終的には訴訟や強制執行などの法的手続きをとることが必要になる場合もあります。そのため、債権者が自力で不履行となった債権を回収するのは大きな負担となる可能性があります。
専門の業者に依頼することで、債権者に負担がかかることなく、円滑に債権回収を実現できる可能性が高まります。
なお、債権回収業務は弁護士法第72条に規定される「法律事務」に該当するため、弁護士しか行うことができないのが原則です。
ただし、司法書士法やサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、弁護士以外の一定の業者についても、例外的に債権回収代行が認められています。
2、債権回収代行を業者に依頼すべきケースとは?
債権回収代行を専門の業者に依頼すべきなのは、債権回収が滞り、自力での回収が難しい場合です。よくある具体的なケースとしては、以下のような場合が考えられます。
-
(1)貸付金の返済が滞った
銀行や貸金業者は、貸付金の返済が行われない「貸し倒れ」が常に一定の確率で発生しますので、その都度または定期的に、債権回収を外部の業者に委託して行っています。
また、銀行・貸金業者以外の会社でも、役員などの関係者に対して貸し付けを行うケースがあり、その貸付金の返済が滞った場合には、債権回収代行のサービスを利用するとよいでしょう。 -
(2)利用料金の支払いが滞った
携帯電話会社、Webサービスの運営会社などは、大量のユーザーを相手にサブスクリプション型のビジネスを展開しています。
当然ユーザーの中には、途中で利用料金を滞納する人が出てくるので、専門業者への債権回収代行へのニーズが発生します。 -
(3)売掛金の入金がない
売掛金が期日どおりに支払われない場合、特に中小企業では、たちまち資金繰りに窮してしまう可能性が高くなります。
日々の営業・業務を行いながら債権回収を自ら行うことは、小規模な事業を営む経営者にとっては現実的ではありません。
そのため、債権回収代行を専門業者に依頼して、売掛金の回収を図るケースが多くなっています。
3、債権回収を依頼できる業者の種類
前述のとおり債権回収代行は、弁護士法をはじめとする法律によって規制されたビジネスです。そのため、債権回収代行を取り扱うことのできる業者は、以下のものに限られています。
-
(1)弁護士
弁護士は、債権回収代行を業として扱うことのできる、もっとも代表的な職種です。
債権回収に債務者が任意に応じない場合には、最終的には訴訟・強制執行による回収を図る必要があります。弁護士は法律の専門家であることから、これらの法的手続きについても安心して任せることができます。
また、弁護士には債権回収代行に関する業務範囲の制限がないため、債権額にかかわらず債権回収代行を依頼できる点もメリットです。 -
(2)認定司法書士
認定司法書士とは、「簡裁訴訟代理等関係業務」を取り扱うことについて、法務大臣の認定を受けた司法書士をいいます(司法書士法第3条第2項)。
認定司法書士も債権回収代行を業として取り扱うことができますが、債権額が140万円以下の場合に限られます。
そのため、債権額が140万円を超える場合には、認定司法書士ではなく弁護士に債権回収代行を依頼しましょう。 -
(3)債権回収業者
債権回収業者(サービサー)は、「債権管理回収業に関する特別措置法」(通称:サービサー法)に基づき、弁護士法第72条の例外として、債権回収代行を業として取り扱うことが認められた業者です。
ただし、債権回収業者が取り扱うことができるのは、「特定金銭債権」に関する債権回収代行に限られます。
したがって、特定金銭債権に該当しない債権の債権回収は、債権回収業者に依頼することはできず、弁護士または認定司法書士に依頼する必要があります。
特定金銭債権に該当する債権は、サービサー法第2条第1項において詳細な定義が設けられていますが、大まかには以下のカテゴリーに大別されます。- ① 銀行などの金融機関や貸金業者が有する貸金債権等
- ② リース・クレジット債権等
- ③ 特定目的会社が流動化対象資産として有する金銭債権等
- ④ 法的倒産手続き中の者が有する金銭債権等
- ⑤ 保証会社・金融機関等が有する求償債権等
- ⑥ その他政令で定める特定金銭債権
-
(4)ファクタリング会社
ファクタリング会社は、厳密には債権回収代行を営む業者ではありませんが、不履行となった債権を回収(現金化)するために利用されます。
具体的には、不履行となった債権を債権者がファクタリング会社に売却し、その代金を得ることによって債権回収を実現します。
売却後の債権は、ファクタリング会社が自らの債権として回収を行うため、債権回収「代行」ではないということです。
ファクタリング会社を利用する場合、債務者からの支払いを待つことなく債権を現金化できるメリットがあります。
その反面、一般に高額の手数料が課される傾向にあり、回収金が目減りしてしまうのが難点です。
また、一部には貸金業法などに違反する違法ファクタリング会社も存在するので、十分に注意しましょう。
4、弁護士に依頼した場合の債権回収の流れ
債権回収代行は、業務範囲の制限がない弁護士に依頼するのが安心かつスムーズです。弁護士に債権回収代行を依頼した場合の、債権回収に至るまでの流れを解説します。
-
(1)弁護士から債務者に対して内容証明郵便を送付する
弁護士が債権回収代行を受任したら、まずは債務者に対して任意の支払いを促すために「催告状」を送付します。
催告状は、内容証明郵便により送付するのが一般的です。
内容証明郵便の形で、弁護士名で催告状を送付することによって、債務者に心理的なプレッシャーが生じ、任意に債務が履行される可能性も高まります。
なお催告状の送付には、債権の消滅時効の完成を6か月間猶予する効果があります(民法第150条第1項)。
債権が発生してから時間がたっている場合には、早めに弁護士に相談をして、債権の消滅時効の完成を阻止しましょう。 -
(2)債務者と支払いに関する交渉を行う
催告状の送付後、債務者が任意の支払いに応じる姿勢を見せた場合には、支払い方法に関する交渉を行います。
債務者側に資金繰りが難しい事情がある場合には、依頼者と相談しながら、場合によっては支払いスケジュールの延長や分割払いになどに応じるケースもあります。
しかし基本的には、履行されない場合には法的手段を取らざるを得ないことを明示しつつ、毅然(きぜん)とした態度で債権回収を行うことになります。 -
(3)法的手段に訴える(支払督促・訴訟)
催告状を送付したにもかかわらず、債務者が任意に債務を履行しない場合には、法的手段を講ずることになります。
債権回収の方法として考えられる法的手段には、「支払督促」と「訴訟」の二つがあります。
支払督促とは、書類審査のみの簡易的な手続きによって、裁判所が債務者に対して発する債務の支払い命令をいいます。
支払督促は、時間的コストや費用が軽く済むメリットがある反面、債務者からの異議申し立てが行われると無効になってしまうデメリットがあります。
これに対して訴訟は、裁判所の法廷で債権の存在について主張・立証を行い、主張が認められれば判決の形で債務の履行を強制する法的手続きです。訴訟準備には手間がかかりますが、判決が確定すれば、確実に強制執行の手続きに移ることができるメリットがあります。 -
(4)強制執行をする
支払督促に対する債務者の異議申し立てがなかった場合や、訴訟における債権者勝訴の判決が確定した場合には、強制執行により債務者の財産を差し押さえます。
差し押さえは、債務者の財産を特定して行う必要があるため、事前の財産調査が必要になる場合があります。
弁護士は、民事執行法上の財産開示制度をはじめとして、さまざま方法を用いて差し押さえ対象財産を特定します。
債務者の財産を差し押さえることに成功したら、その財産を換価・処分して債権の弁済に充当し、債権回収は完了です。
5、まとめ
債権回収代行を営む業者にはいくつかの種類が存在しますが、法的手続きによる債権回収を見据えた場合には、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
ベリーベスト法律事務所では、債務者に対する催告、法的手続き(支払督促・訴訟)、強制執行などを全般的に代行し、円滑な債権回収をサポートいたします。
貸付金・利用料金・売掛金などの不払いにお悩みの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 京都オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています